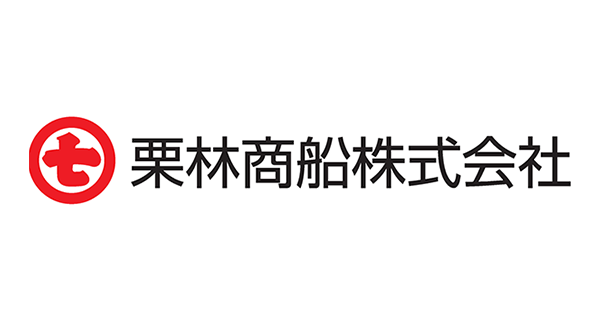【日記リレー2025 vol.19】「自分のペースで」 ~細田実路(4年/法学部政治学科/MF/#42/慶應義塾高等学校) ~

翼からバトンを受け取りました細田実路です。
明学の奥山廉太郎君、立教の奥森太郎君、時には人種を超えて人違いされる私ですが、この部活の何人かにはまだ東南アジアの血が入ったクォーターだと言ったまま、ネタばらしをしていません。おそらく峰岸は今でも信じていると思います。
翼は塾高からの仲で、近くに住んでいることもあり、大山と翼と僕で集まることが多いです。なんと言っても幼稚舎からラクロスをしてきた彼の人脈の大きさは測り知れません。ラクロス協会の方々から、何個上のOB、他大学の選手やコーチまで繋がりがあり、困ったときには彼に相談すれば何とかしてくれるでしょう。そんな彼は今、圧倒的なコミュ力とリーダーシップでアーセナルをまとめ上げ、コーチとしての力量に日々驚かされています。ウィンターが楽しみです。一方でチアの可愛い彼女が最近でき、ウハウハしています。なんで翼が?という嫉妬の声が部内から上がっていますが、僕もそう思います。ですが大人しく見守ってあげましょう。
はじめに、平素より弊部に関わってくださっている監督、社会人コーチ陣、OB・OG、ラクロス協会、保護者の皆さまへ、心より感謝申し上げます。全日優勝どころか、Final4敗退という結果となってしまい、ご期待に添えず誠に申し訳ございませんでした。しかしながら、慶應男子ラクロス部は続いていきますので、今後とも変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします。
本題に移りますが、私は何か大きなことを達成してきたわけではなく、大層なことは書けません。それでも、この1年は自分の7年間のラクロス人生の中で間違いなく最も成長した時間でした。特に6月に帰国して復帰してからの4ヶ月間は最高に楽しかったです。ただ、もう少しだけ続いてほしかったと、引退して6日経った今も考えてしまいます。だからこそ、僕と似たような境遇で今悩んでいる人に、少しでも刺さってくれるような文章を書きたいと思います。
ダラダラと書きそうなので、最初に伝えたいことを書きます。
「他人と比べすぎず、自分のペースで、自分らしく戦うこと」
________________________________________________________________________
まずは、自分の大学からの人生を振り返る。
正直に言えば、僕の大学1・2年はドブに捨てたようなものだった。最初に来る文章として相応しくないが、自分を見てきた先輩・同期または後輩までもがそう思うだろう。塾高から早くラクロスを始めたのに、アーセも含めて誰よりも”スタート”が遅かった。
入学当初は、留学をして今まで勉強してきた英語で新しい世界を見てみたいと思い、部活に入るつもりはなかった。そもそも慶大のレベルの高さに自分はついていけないと思っていたし、翼や関根たちが早くから練習に参加しているのを横目に、別の大学生活を思い描いていた。そんな中、塾高組のトライアウト前日に増成から「とりあえず受けてみなよ」と電話をもらい、軽い気持ちで受けたのが始まりだった。結果、合格して入部したが、そこからの2年間はまったく伸びなかった。
それもそのはず、先輩に憧れを抱いて入ったわけでもないし、それがなくても戦える強い芯もなかった。”部活をやっている感覚“だけを味わっていた。
その時には、太夫や大山はAやBにいて、何なら後輩の大類や岸、アーセの池田や海がとっくに抜かしていた。そんな事実から目を背け、なんとかなるだろうという淡い期待を抱き、多田の言う茹でガエル状態になっていった。自信もだんだんどっかに消えていき、ラクロスが楽しくなかった。交換留学の準備を言い訳にして、とにかく自分の現状を正当化しようとしていた。
転機は留学だった。
留学を通じて、自分のアイデンティティについてこれまで以上に考えるようになり、今まで長い時間を共にした慶應ラクロス部という存在の大きさに気づいた。離れてみて初めて、自分にとってそれがどれほど大切な場所だったのかを痛感した。
現地では、今までなら見なかったであろう慶應の試合配信をオンラインで追いかけていた。池田の全日のビハインドを見たときは、思わず友達と部屋で発狂したのを覚えている。後輩・同期・先輩を問わず、彼らが活躍する姿を見るたびに、留学中の孤立していた状況も相まって「早くチームに戻りたい」と強く思った。その気持ちが、現地でラクロスをする大きなモチベーションにもなっていた。
帰国してAチームに上がってからの毎日は、刺激的で本当に楽しかった。この期間が、7年間のラクロス人生の中で最も成長できた時間だったと思う。裕太さんや清さんをはじめ、コーチ陣や後輩を含めたAチームの選手たちからは、毎日新しい発見があった。オンとオフの切り替えが徹底され、練習の強度も高く、全員がアスリートとしての意識を持っている。そんな環境の中で、今まで手の届かなかった場所にいた同期や可愛い後輩たちと一緒にラクロスができるのが本当に楽しかった。
本当であれば、アメリカでラクロスをやって、帰国してスタメンで活躍したという綺麗なストーリーを描きたかった。しかし現実は甘くない。レベルの高さに圧倒され、思うように通用せず、日々試行錯誤を繰り返した。全学までにファーストセットに入る気持ちで、毎日もがいていた。
引退がかかっていたFinal4では、ギリギリでベンチ入り。悔しさはあったが、ここは試合に出る仲間たちに託し、命をつないでもらい、またそこから頑張っていこうと思っていた。
しかし結果は完敗。自分は1秒も出場できずに終わった。先を見据えていたがために、ここで本当に終わってしまうことが信じられなかった。
遅すぎたけれど、ようやくスタートラインに立てた自分の挑戦がここで終わってしまうのが辛かったし、1秒も出場せずに、何もできずに終わってしまった無力さやAチームのメンバーと一緒にラクロスができないことも辛かった。そのすべてが、笛が鳴り終わった時に、涙と一緒に込み上げてきた。
試合後のロッカールームで、裕太さんから「泣いている人は十分やりきれてない証拠」と話されていた。1・2年をドブに捨てた私にとって、その言葉はまさに胸に刺さった。Aになってからも、振り返ればもう少しできたことがあったと思う。
ラクロス人生としては不完全燃焼という形に終わったかもしれない。それでも、このラクロス部での学生生活、特に最後の一年は、もう二度と味わえないほど濃く、貴重な時間だった。
ここからは、自分がこの1年で大切だと感じた2つのことについて書きます。不完全燃焼した人の話なんかと思いますが、僕自身に欠けていた部分であり、同じような悩みを抱えている選手の力に少しでもなればと思います。
心の持ち方について
ラクロスは技術5割、メンタル5割だと思います。
Aチームで活躍している人は技術はもちろん、みんなメンタルが鬼強いです。最初からある人はいません。小さな成功から積み上がっていっているはずです。
僕は留学前までは、上手い人を見るや否や、特に特別な武器を持っていなかった自分は何もできないのだとネガティブな気持ちになっていました。部活にいる以上、誰かと比べられるのは当たり前で、そのプレッシャーは自分の中でかなり大きかったです。同期も、どんどん上手くなっていって、卑屈になっていく。塾高組なのにCチームというレッテルをどこかで意識してしまい、周囲の何気ない会話にも、自分のことを話しているのではないかと過敏に反応するようになっていました。そうした自意識の強さが、自信のなさに拍車をかけていたように思います。その度に自分なら大丈夫と言い聞かせて、何の身も詰まっていない見せかけの自信を取り繕い、メンタルを安定させていました。しかし、実際は焦って、本来の力を発揮できず、たくさんあった成長する機会を捨てていきました。
なんとかなると思っていたその自信過剰は努力すら怠り、言い訳ばかりの選手に変えていってしまいました。留学の準備が忙しいとかそんな変な言い訳を作って、努力するのもやめていくようになりました。
だけど、アメリカに留学して、今までの自分を知らない人たちしかいない環境で、周りから評価される大きなプレッシャーを感じずに、気軽にプレーすることができました。とにかく、相手と比べずに、自分だけを見て、lock inすることだけを意識しました。ミスっても笑って励ましてくれるチームメイトに、「誰も君のミスなんて気にしない。もっとのびのびやれよ」と声をかけられて、そんな言葉にもかなり助けられたのを覚えています。
自分の中では、アメリカの環境は間違いなく自信に繋がったと思います。
また、帰国してからはなかなか抜けない1on1に苦労しました。簡単にダッチで抜けてしまう人たちを見て、羨ましかったです。でも、見方を変えました。1on1で抜けなくても、半身さえ抜ければ、打てるし、相手にとっても予測不可能なプレーができる。そう裕太さんから教わりました。気持ちは楽になった。周りを見ていると、自分に合ったプレーでもないのに、マジョリティの人達のプレーが答えだと思い、答えが一つしかないと思い込んでしまいます。でも、意外とそんなことはなくて、答えは何個もあり、焦らず自分に合ったものを探していく。そして、自分のペースで、自分の中の自信を育てていくことが大切だと学びました。
努力について
短い間でしたが、Aチームに在籍して、他のチームからは見えなかった、みんなの努力の量が、伝わってきました。Aオフェンスの中では、橋山のパソコンのデスクトップ画面が高層ビルを下から撮った写真だったり、向こうが見えない長いストリートの写真だっただけで、「上しか見てない」「先を見すぎている」など、アスリートすぎるといじられていますが、いじっているみんなもアスリートです。
留学先のチームでは、毎回練習や試合前に、選手がquoteを述べる慣習があり、そこで気にいった言葉があります。
「Extraordinary(=並外れた、桁外れた)とOrdinary(=平凡な)の違いは”Extra”というほんの少しの差である。」
Extraordinaryな人を想像すると、スター選手など手の届かない存在が浮かんできますよね。しかし、彼らがやっていることは、この小さな物事(extra)の積み重ねであり、これをするかしないかが並外れた人になるか、平凡な人になるかの分かれ道であるということが、このquoteが指していることになります。
私は、自分が足りなかったショットを鍛えるために、公園にあるゴールを使って、シュート練習を一人でずっとやってました。結果、今まで張り付かなったショットのクレードルでボールが張り付く感覚を7年目にして覚えて、速くなりました。ショットが少し上手くなっただけでもラクロスは楽しくなりました。ちなみにですが、アメリカの人たちはみんなショットがうまかったです。単に早いだけじゃなくて、決めきりがうまく、得点力はかなりありました。ショットクロックがあるものの、ハイスコアのゲーム展開になるのは、そういうところもあるんだと肌で実感しました。
ショットだけじゃなくて、壁当ても、薬物中毒のホームレスの隣でやり続けました。食事もとにかくたくさん食べて、6kg増やしました。
自分なりにアメリカでextraの努力をしましたが、帰国後に、Aチームに上がってからはもっと色々そのextraの努力をしている人を見ました。特に海はすごかったです。あれはチリツモを体現していますね。
体調管理も、ストレッチも、壁当ても、食事管理も、メニュー間の切り替えも、ジムも、その日だるいなって思ったことも全てがそのextraです。その努力は必ず自信につながると思います。
また、extraの中には頭を使って考え続けることも含まれています。Extraの努力が体に染み付いていくと、形だけが残って、本来の意味を見失いがちになりますが、常に考え続けましょう。
あと、関根や糟谷も言っていましたが、ただ努力するだけで満足するのではなく、報われるまで努力する必要があると思います。
総じて、言いたいこととしては、冒頭に述べた通り、
「隣の芝はいつどこに行っても青く見えるが、それは仕方のないこと。
今自分の芝が枯れていても、自分のペースで、自分らしい庭を作ること。」
少しカッコつけましたが、この競技をやっている限り、周りと比べられることは避けられません。時には陰口を言われたりもします。それでも、焦らず、自分の芝を耕し続けること。
僕が書いた “extraの努力”の話は、そのための支えになるものだと思っています。
特にプレッシャーに弱かった私にとっては、これ以上、的を得ている言葉はありません。
最後に恒例の感謝コーナーです。
両親へ
部活から留学まで、今まで何一つ不自由ない生活をさせてくれてありがとう。試合にはあの中西家に次ぐ観戦参加率だったのに、いいところを見せられずに終わってしまい、申し訳ないです。学生生活はまだ続き、もう少しだけ迷惑をかけますが、よろしくお願いします。
同期へ
途中腐っても、留学に行っても、一同期として対等に振る舞ってくれてありがとう。みんな、活躍する場所は違えど、同じ強い信念を持っていて、刺激をもらっています。モラルは壊滅的にないですが、近年稀に見る仲の良すぎる代だと思います。本当に同期に恵まれました。これからもよろしく!
Aにいる後輩へ
本当にみんなうまくて、色々勉強させてもらいました。僕から何もアドバイスすることはありませんが、せめて言うとすれば、23歳の先輩をいじめるのはやめましょう。みんな可愛いくて、短い間だったけど、楽しかったです。
Bにいる後輩へ
短い間だったけど、お世話になりました。一昨年よりもさらにフレッシュな感じがあって、好きでした。なんでも挑戦しやすい環境だから、いっぱい挑戦して失敗して、これからどんどん伸びてAで活躍してください。怪我であったり、干されたり、色々理由はあると思うけど、周りに急かされないで、自分のペースで、頑張ってください。
スタッフへ
留学先のチームはスタッフがいなくて、選手とコーチで全部回していました。トレーナーも医者が週に一回来ていただけで、ASもいないから練習の録画もされず、慶應の環境は素晴らしいと思いました。いつも快適に練習をさせていただいて感謝しています。
他にも個人的に書きたい人はたくさんいますが、今度直接会ったときに伝えたいと思います。あと僕は3年生なので3年生の人達は同期会に呼んでいただけると嬉しいです。待ってます。
次はお待ちかねの堀川元君です。彼の表の顔は慶應の学生として、仮面を被って、暮らしておりますが、本当の顔は諜報工作員として裏の世界で暗躍しています。物事の裏には全て彼がいるとも思っていた方がいいです。諜報工作員として鍛え上げてきた、何が起きても顔色ひとつ変えない冷静さと頭の回転の速さで現在はオフェンスコーチという形でCチームを引っ張っています。来週には早稲田との育成リーグ決勝が控えており、その思いがこもった素敵な文章期待してます。それではよろしく!