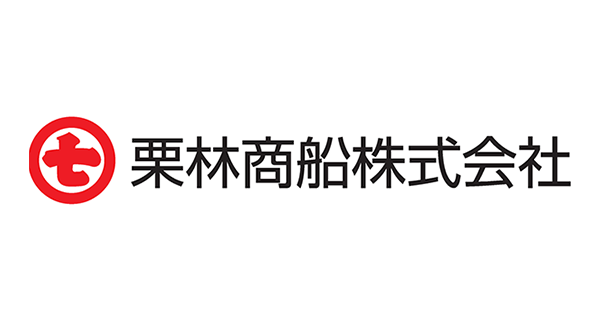【Pioneer’s Session VOL.7】飯田大樹 × 水野翔 × 中本孝太郎 <前編>

平素より慶應ラクロスへ多大なるご支援、ご声援をいただきありがとうございます。
第7回となる今回は、33年の歴史を誇る早慶戦を支えてきた「実行委員」をテーマに、卒業生からは飯田大樹さん(2012年卒)、水野翔さん(2024年卒)、現役部員からは中本孝太郎(3年)に参加していただきました。
今回は前半の様子をお届けします。
ぜひお楽しみください。
自己紹介をお願いします。
中本:
今年度の早慶戦実行委員長を務めます、3年の中本です。
お忙しい中、お時間いただきありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。
水野さん:
“Strive”シーズンのディフェンスをやっていました水野と申します。
僕が大学三年生だった時の早慶戦で副委員長を担当させていただきました。委員長は早稲田の坂くんで一緒にやっていました。よろしくお願いいたします。
飯田さん:
水野さんは何年度の早慶戦を担当していたのですか?
水野さん:
2022年度の富士通スタジアム川崎で開催された早慶戦ですね。
飯田さん:
なるほど。その時は無観客?
水野さん:
4年ぶりの有観客でした。
飯田さん:
4年ぶりか。なるほど、なるほど。
飯田さん:
2012年卒の飯田大樹と申します。僕は2011年の第19回早慶戦の委員長をやっていました。ちなみに、実は今年の早慶戦に指1本分ぐらい関わらせてもらっていて。ちょっと横目で今年の中本さん含めた学生の運営みたいなところを見ながら今日は参戦させてもらっております。本日はざっくばらんに当時のお話をできたらなと思います。
よろしくお願いします。

当時の早慶戦を教えてください。
中本:
今年の早慶戦では”お祭り”を意識しています。
今年度は観客の皆様にスティックバルーンを配って応援を盛り上げたり、その他は選手目線になってしまうんですけども、写真を撮った時に、背景が白と赤で分かれていたりしたら映えるだろうなみたいな感じの、軽い思い付きから始めて、現在はそれが実際に形になってきました。
もう1つ、新しい施策としてテレビ朝日さんでのCS放送が最も大きいことだと思います。今年からテレビ朝日さんのOBの方からお声がけいただいて、CS放送で早慶戦をぜひ放映したいという連絡をいただきました。実際に色々なOBの方々、藤岡さん(※藤岡憲二 現大会委員 早稲田OB 2014年卒)や、保坂さん(※保坂光信 現大会委員 慶應OB 2001年卒)、慶應の澤本さん(※総監督)だったりと協議を重ねて、今実現に向けて動いている最中です。そこで小さな問題が色々生じているんですけれども、現在実現に向けて動いているところです笑。
当時、実行委員で新たな試みなどはありましたか?
水野さん:
僕の時は、コロナが明けて初めての有観客でした。その前の年は無観客で日吉でやっていたんですけど、「まず有観客でやるとしたらどこでやるの?」「日吉じゃできなくね?」みたいな話から始まりました。そこで、大会委員の大人の方々がなんとか川崎の富士通スタジアムの方と連絡を取ってくれて、やっと始まったみたいな感じでした。
目新しいことができたわけではなかった年だと思うんですけど、唯一あるとしたら、Peatixのオンラインチケットだと思います。多分、今年もPeatixを使ってもらっていると思うんだけど、そこが僕の代が導入できた大きいことだったかなと思います。
飯田さん:
ちなみにちょっとお伺いしたいんですけど、当時は日吉だと有観客ではできなかったんですか?
水野さん:
実は、大学側の許可が取れなくて。コロナ前だと7,000人〜8,000人ぐらい来場していただいていたっていうこともあり、当時はまだコロナの第5波みたいなところで、「ここでまたクラスターができたらどうするの?」と、かなり日吉でやるのは厳しかった記憶があります。
かなり昔のことで、確かそんな話があったような気がします笑。
飯田さん:
その時の水野さんたちの気持ちとして、無観客で日吉でやるっていう選択肢もあったんじゃないですか?
水野さん:
そうですね、ありました。
飯田さん:
有観客にするっていうのは、学生側の意思だったのか、大人側の意思だったのか、どうだったんですかね?
水野さん:
学生も大人の方も「有観客でやりたい」という思いはありました。
前年が無観客で、「ちょっと寂しかった」と感じて、やっぱり有観客でいろんな人に来てもらって、リーグ戦前のお祭りみたいな感じでやるのが早慶戦だよね、みたいな話にはなっていました。
僕の1個上の代も、有観客を望んでいると伺っていたので、やっぱり「有観客でやりたい」という思いは学生の方がかなり強かったと思います。
どうにかできないかというところを汲んで、源学さん(※当時大会委員 慶應OB 1995年卒 第1回早慶戦実行委員長)や、保坂さんがいろいろ対応してくださっていたので、かなり感謝しています。
飯田さん:
なるほど。あともう1個質問で、YouTubeの放送ってやっていましたか?
水野さん:
YouTubeでの配信はやりました。
自分が携わった早慶戦の前年が無観客だったのでYouTubeライブを始めて、それを引き継いで僕の代でもやってます。
飯田さん:
そうなんですね。
僕の時はもちろんYouTube配信とかも当然なくて笑。たぶん今と全然違うところで言うと、当時の目標観客数が3,500人だったところだと思います。普通にやったら3,000~4,000人入れるキャパがあるのに僕の前年は雨が雨降ってしまい、2,500人ぐらいしか入らなくて。なので、僕の代は3,000人とか4,000人ぐらいを最大キャパとして目指していた記憶があります。そういう意味では、全然もう規模感が違うんだよなって今思いました。

ほんとに拙い記憶をたどりながら言うと、僕の代から始めたのは、めっちゃ細かいんですけど、キッズスペースを設けたことです。そこでは、授乳スペースとかオムツ替えスペースみたいなのが全然なかったので、日吉の協生館と協力をしながら、控え室の1室を使って、「ここでカーテン締め切ってオムツを替えられるスペースにしましょう」みたいなことをやった記憶があります。
当時は、早慶戦にくる観客が現役の学生や、友達か、熱の入ってるOBしか来ないみたいなのが課題で。だから、より気楽に来られるイベントにするにはどうすればいいか、みたいなことを学生の中では話し合ってた記憶がありますね。
水野さん:
そういった運営にとってベースとなる部分に配慮していただいたおかげで、僕の代で言えばPeatix導入でオンラインチケットを買ってもらったり、中本の代でテレビ放映するのに至っていると思います。
ベースを今までの代で作ってきてもらった感覚は、すごく僕の代でもありました。
源学さんや、保坂さんからのノウハウはもちろんあると思いますし、今までの早慶戦を作り上げてきていただいた先代には、すごい感謝の気持ちで当時いっぱいでした。
今も後輩の試合を見る時に、「やっぱ昔からの積み重ねってすげぇんだな」って感じますね笑。
飯田さん:
早慶戦に関わって一番思ったのは、「裏でめちゃめちゃ大人って動いているな」ってことをすごい感じました。
源学さんとか僕が辞めたあとも続けて都合30年間くらい早慶戦に携わり続けるって、ものすごくすげぇことだよなって思いました。同時に、OBOGの方への感謝を学生だからこそ感じる気はしましたね。
中本:
ちなみに、まだYouTubeなどの配信もない時代に、気軽に慶應のOBや、身の回りの人以外にアプローチしたいとなった時にどのような集客の仕方を行っていましたか?
飯田さん:
すごい古典的で笑。
当時は、紙のチケットだったので、ノルマっていうわけではないですけど、「周囲にチケットを売ってこい」みたいな感じでした。
自分の周囲は早慶戦への熱もあったし、僕の時に皆さんと同じく体育会だったんですけど、体育会になってまだ4、5年目とか日が浅かったので、より学生の中での注目度も上がっていました。周りの人に声をかければ来てくれるみたいな感じでしたね。なので、口コミが結構メインでした。さっきのキッズスペースみたいなこともそうですし、口コミで呼びやすくしたり、今までよりも来やすくすることへの配慮が結構大事だったと思います。
逆に今の集客ってどうやってるんすか?SNSや、主将会とかでも告知してるって話もある中で、他に友達や、学生間、他チームとかには、どんな告知の仕方をしているんですか?
中本:
現在はインスタグラムがおっしゃる通りメインです。
そこから、全大学の男子部・女子部をリストアップして突撃してます笑。
飯田さん:
DM送ってる?
中本:
早慶男女で分けてDMを送っています。例えば僕は今、男子3部の大学を担当していて、自分のアカウントでDMを送っています。返事をもらえればラッキーで、もらえなかったら、また別の方法を考えようと思っています。でも、まだ全然チケットが残っていて。直前に買う方が多いとは思うんですけど、現在300枚ほどしか売れていない状況です。
今回お二人にアドバイスをいただきたくて、何か良い方法があればお伺いしたいなと思っているんですけれどもいかがでしょうか?
水野さん:
今、聞いていて思い出したんですけど、確かに1ヶ月前ぐらいにチケット販売を始めてから全然買ってくれなくて、めちゃくちゃ焦った記憶を思い出しました笑。
当時は、インスタでDMを送って突撃みたいなことまではしてなかったと思うんですよね。でも、前日とか1週間前ぐらいになってきたら増えると思います。
さっき自分の代の記録を確認したんですけど、2週間前でだいたいチケット2,200枚ぐらい買ってもらっていて、そのまた1週間で7〜800人増えてみたいな感じでした。
結構、急がせたり強制しても、買ってくれない人は多いと思うので、そこはあんまり焦らず、地道にDMするのはめちゃくちゃ効果的かと。僕の1個下の代から、インスタグラムに一段と力を入れていて、影響力はフォロワーの増え方を見てもかなりあると思います。そこは一旦安心して、自分たちが今できることをやれば良いのかなと。
飯田さん:
そうですよね。直前になって買う人がほとんどだと思います。
水野さん:
ごめんなさい、僕もまだ買ってないんで、この対談が終わったら買います笑。
早慶戦委員になったきっかけは何ですか?
中本:
僕は高校からラクロスをやっていて、塾高1年生の時から早慶戦は見てました。
初めて早慶戦を見た時に、舞台や開会式での挨拶をしている姿を見て、「自分が大学に入ってこのままラクロスを続けるのであれば、早慶戦を先頭に立って盛り上げたいな」っていう思いがあり、大学に入ってからも、ラクロス部にいる中で”何か大きなことに携わりたい”と考えてました。その中には、他にも大会委員だったり、現在慶應ラクロスが力を入れているマーケティング部門だったり、いろいろある中で、塾高時代から見ていた“早慶戦”を一番意識するようになっていました。早慶戦実行委員の応募がかかった時に、すぐ手を挙げたっていう感じですね。
水野さん:
なるほど。
僕も結構、同じような感じですね。
塾高の時に、立石さんを始めとした塾高からのスター選手が多く活躍している早慶戦を見て「これに出られたらベストだな」って思っていました。でも、大学に入って、自分が大学3年生になった時に一個上の代のの早慶戦に自分が出られるかどうかを考えた時に、あんまり自分は上手い方ではなかったので、「貢献できるとしたら、大会の運営の方かな」と思って。実際、大会の裏側とか運営側って見たことないなっていうのもありました。
学生リーグの決勝よりたくさん人数が来ることを聞いてたので、そういった大会の運営に携われるなら、選手としてじゃなくても運営側として貢献できたらいいなと思ってました。
当時は、一個上の早慶戦実行委員をやられていた中西宙さん(※2023卒)に恥ずかしかったのか「誰もいなかったらやります」って僕が一番に言って、その流れで実行委員になったって感じですね笑。
飯田さん:
僕は、自分で手を挙げたっていうよりかは、1個上の先輩が指名で「お前一緒にやろう」みたいな感じで誘ってもらいました。「その人が言うんだったらやろうかな」って思ったってのが、ぶっちゃけたところです笑。
僕は大学からラクロスを始めていますし、大学の時にたぶん日吉の陸上競技場ができたか、まだできたてだったので、あそこの会場でラクロスの早慶戦をやるってこと自体が、そこまで浸透していませんでした。
その先輩が「やってみよう!楽しいぞ!」みたいな感じで誘ってくれたので始めてみました。別にそれがきっかけというわけではないんですけど、今は新卒で入ってからずっと同じ広告代理店に勤めています笑。

実行委員の経験は、その後の人生でどう活きていますか?
飯田さん:
早慶戦での経験っていうのは、実は今の仕事にもベースとして生きていたりするので、すごく貴重な体験をさせてもらったなと思っています。
それまでは選手だけの視点しか持たずに練習や、試合とかにも取り組んでいたんですけど、実行委員をやってみて初めて、”運営してくれる人がいるからこそ、それを見に来てくれる人がいる”ことを体感しました。きっかけは「誘われたから」っていう感じなんですけど、今になってみるとすごく貴重な経験をさせてもらったなと思います。
水野さん:
僕は4月で社会人2年目なんですけど、早慶戦実行委員やっといてよかったなって思うのは、”周りの人に頼ることが当たり前になった”ところです。
もちろん選手としても、先輩にいろいろ聞いたり、指導してもらったりってのはあったんですけど、大会運営は自分から聞きにいかないと分からないことが多すぎて。例えばPeatixの件だったら、早慶戦実行委員で手伝ってくださる大人の方も、まだやった経験がなくて。1期前のリーグ戦の決勝で、日本ラクロス協会の方が使っていたので、そこに突撃して聞きに行ってみたり。
あとは、「今回外部の会場を借りてやるけど、どうするんだろう?」みたいなところを、施設の方に聞きに行ったり。本当にいろんな方に頼りっぱなしでやっていました。
でもそれって、僕が会社でいちばん下になった去年1年間も、その経験のおかげでいろんな人に聞ける、変なプライドも持たずに聞けるようになったのが、早慶戦をやっていてすごくよかったなって思うことのひとつです。
飯田さん:
それは僕もすごい感じますね。
「わからないから、わからない」で片付けるのは簡単だけど、わからないからって、もじもじしていても何も物事は前に進まないんだなってすごく思いました。決めることも多くて、「これまだ決まってないの?」とか言われても「いや、知らない」とか思うけど、知らないまま放っておいても、パンフレットは出来上がらないし、会場の申請もできない。
だから、もじもじせずにわからないなりに「教えてくれ」とか、「やってみて失敗したらもう一回やればいい」みたいな精神は、そこで身についた感覚はあるかもしれないですね。
前半はお楽しみいただけたでしょうか。
後編は一週間後の5月12日の投稿を予定しております。
乞うご期待ください。